こんにちは。つつじピアノ教室の森田ひかりです。
今回は、譜読みが早くなる方法についてお伝えできたらと思います。
「うちの子、譜読みが苦手で…」
「子どもの譜読みが遅いので、練習に付き合う親が疲れてしまう」
「耳で覚えるタイプなので、楽譜を見る習慣がついていない」
などのお悩みを抱えていらっしゃる保護者の方も多いのではないでしょうか。
譜読みが早いと、その分曲を仕上げるスピードが上がりますし、
譜読みが遅いことで感じるストレスも減り、心理的にも新しい曲に挑戦しやすくなります。
ピアノを続けていく上でも、やはり譜読みが早いと、
小学校の高学年など忙しくなってきて充分な時間が取れないような時期にも続けやすくなると思います。
私自身、子どもの頃はどちらかというと耳で覚えて曲を記憶することが得意なタイプでしたが、曲が難しくなるにつれ、譜読みの重要性に気づき、譜読みが早くなるように改善していきました。
それでは、どのようにすれば譜読みが早くなるのでしょうか。
いくつかポイントがありますので、説明していきたいと思います。
①楽譜の線(せん)と間(かん)の仕組みを理解する
当教室でピアノを習う場合、まずは線と間の仕組みを理解してもらいます。
譜読みが苦手なお子さんの場合、そもそも五線の仕組みを理解できていないということもあります。
4歳くらいのお子さんでも、わかりやすく説明すれば、線と間の概念を理解して音符を読むことが可能です。
②音をランダムでも読めるようにする
五線の仕組みが理解できると、よくあるパターンとして、真ん中の「ド」から順番に「ドレミファソラシ…」という具合に数えていくために、高い音が出てきた時に音符を読むのが遅くなる、ということもあります。
楽譜のこの場所にある音は「シ」というように、出てきた単音をすぐにわかるように覚えてしまうと早いです。
レッスンでは音符カードを使って、ランダムに出された音を弾いていくというゲームをして、楽しく音を覚えるようにしていきます。
また、音を覚えるためのドリルのような教材を使っていくのも一つの方法かと思います。
ミッキーといっしょ-たのしいおんぷカード-
音楽の基礎学習プリント 書いて覚える徹底!! 譜読
③音を相対的に読む・まとめて読む
音をランダムに出されてもすぐにわかるようにする一方で、音を相対的にも読めるようにする…
その両方の読み方ができると譜読みは早くなります。
1音1音を拾って読むのではなく、前の音からどのくらい上がったか下がったかを認識して、まとめて図形として読めるようにしていくようなイメージです。
メロディーだけでなく、和音も同様に、1音1音を拾って読むと時間がかかってしまいますが、図形として読めるようになると早いです。
④目の使い方を習得する
譜読みが遅い理由として、目の使い方が関係していることもあります。
音を弾く瞬間に読むと、どうしても遅れてしまいますので、
これから弾く音の少し先を目で追って弾くようにします。
その時に、頭の中で音をイメージすることも大切です。
また、楽譜と鍵盤の間を、首を上げ下げして行ったり来たりすると、その分楽譜を読むのが遅れてしまいます。鍵盤上で手のポジション移動がないところでは、できるだけ鍵盤を見ずに楽譜を見るようにして弾くと効率的です。
それから、片手ずつに分けてそれぞれの譜読みばかりするのも、右手パートと左手パートの両方を同時に読んでいく目の使い方が習得できなくなってしまいがちですので、
両手の曲に進んだら、可能な範囲で最初から両手での譜読みも取り入れていくと良いかと思います。
⑤沢山の曲を弾いて慣れる
譜読みは訓練で早くなります。最後はなんと言っても慣れが大切になってきます。
小さなお子さんが日本語を覚えたての時は、一語一語を区切って読んでいくので時間がかかりますが、色々な本を読んでいくうちに、次第に言葉をまとまって読むことができるようになり、読むスピードも上がっていきます。
楽譜を読むのも同じように、色々な曲を弾いていくうちに、譜読みが早くなっていきます。
簡単な曲を沢山弾いていくことで、譜読みも早くなっていくことと思います。
譜読みは、曲を仕上げていく過程の一部分ではありますが、
遅いとモチベーションも下がってしまいがちですので、小さな頃から譜読みに苦手意識を持たないようにレッスンしていくことは大切だと感じます。
楽譜を読むときに、音がわからない生徒さんがいたら、答えを教えてしまうことは簡単なのですが、わからない理由を認識して、根気強く「考え方」を教えることが、譜読みをできるようにする近道だと思っています。
生徒さん達には、楽譜の読み方をマスターして、色々な曲にチャレンジしていってほしいと思っています。


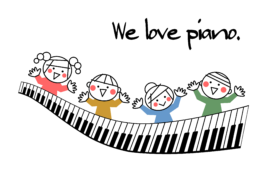




この記事へのコメントはありません。